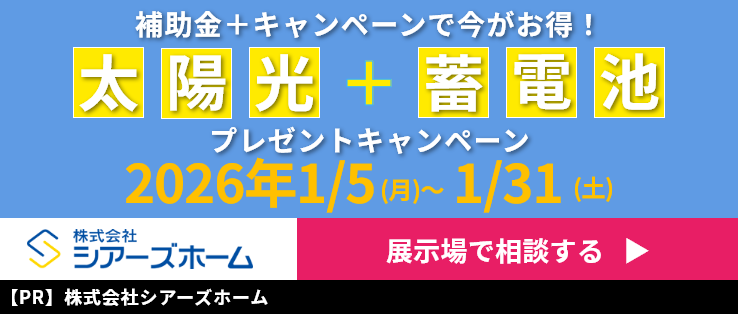ユニバーサルデザイン住宅の考え方:誰もが暮らしやすい住まいづくり

ユニバーサルデザイン(UD)とは、高齢者や障がい者、子育て世代など誰もが快適に使える製品・環境を目指す考え方です。住宅の分野では、バリアフリーと混同されがちですが、UDは段差を取り除くだけでなく、家族構成や将来のライフステージに応じて柔軟に対応できる設計を重視します。
例えば、車いす利用者だけでなく、子どもが安全に動き回れるスペースづくりや、高齢者が転倒リスクを減らせる手すり・照明の配置など、より包括的なアプローチが求められるのが特長です。
本記事では、ユニバーサルデザインとバリアフリーの違いや、将来に備えた間取りや設備の工夫、さらにスイッチやドア位置などの細かな要素まで、具体的な事例を交えて解説します。誰もが暮らしやすい住まいづくりのヒントを、ぜひ探してみてください。
目次
ユニバーサルデザインとバリアフリーの違い
引用元:NIJIBOX BLOG
ユニバーサルデザイン住宅を考えるうえで、しばしば耳にするのが「バリアフリー」との違いです。どちらも高齢者や障がい者をはじめ、多様な人々が安全かつ快適に暮らせる環境づくりを目指している点では共通しています。
しかし、両者にはアプローチの範囲や着目点に違いがあるため、家づくりを計画する際にはその相違点を把握しておくことが大切です。ここでは、まず「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」の定義や目的を整理し、それぞれがどのような住まいづくりを想定しているのかを解説します。
バリアフリー:物理的・心理的な障壁を取り除く考え方
「バリアフリー」とは、本来利用者にとって障壁(バリア)となるものを取り除き、物理的・心理的なハードルを低減することを指します。たとえば、車いす利用者や高齢者の歩行を想定し、段差をなくす、手すりやスロープを設置するといった具体的な改修が代表例です。バリアフリーは、もともとある環境に存在する「移動や行動を阻害する要素」を取り除くためのアクションが中心であり、以下のような場面で活用されることが多いでしょう。
•車いす利用者用のスロープ
玄関や建物の出入口にスロープを設置して段差を解消し、車いすの出入りをスムーズにする。
•手すり・段差解消
階段や浴室などで転倒リスクを軽減し、高齢者や歩行が困難な人でも安全に移動できるよう配慮する。
•心理的バリアの解消
表示やサインを大きくする、色分けを行うなど、視覚障がい者や読み書きに困難を抱える人でも理解しやすい情報提供を目指す。
バリアフリーの特徴は、どちらかと言えば「既存の問題や障壁を後から補う」という発想が強い点にあります。たとえば、築年数の経った家をリフォームする際に、段差の解消や手すりの取り付けを行うことで、既存住宅を“より住みやすい空間”に変えていくといったケースが典型例です。
ユニバーサルデザイン:最初から誰でも使いやすい設計
一方、「ユニバーサルデザイン(UD)」は、最初から多様な利用者を想定したうえで、誰でも使いやすい環境や製品をデザインするという思想が基盤となります。車いすやベビーカーを使う人、高齢者、子ども、障がいのある人など、さまざまな身体能力や生活状況を前提に、段差や操作方法、動線、情報表示などを総合的に検討し、最初からできるだけ広い範囲の人々にとって快適に利用できるよう設計していくわけです。
具体的には、下記のような工夫が挙げられます。
•広い通路幅・開口部
車いすがすれ違える程度の廊下幅や、ベビーカーを押していてもスムーズに通れるドア幅などを設計段階から確保。
•操作のしやすさ
ドアノブをレバーハンドルにする、スイッチ類を片手で押せるようにするなど、体力や身体能力に依存せず誰でも扱いやすい形状に。
•段差を極力なくす
バリアフリー的な改修が必要になる前に、あらかじめフラットな床構造を選ぶなど、設計段階で障壁を作らない。
つまり、ユニバーサルデザインは「後から障壁を取り除く」のではなく「最初から障壁がない状態を目指す」というアプローチが中心となります。これにより、高齢者や障がい者だけでなく、健常者にとっても使いやすい環境が構築され、家族や友人、来訪者など誰が訪れても共に快適に過ごせる住まいが実現できるのです。
高齢者・子ども・障がい者対応
ユニバーサルデザイン住宅を考えるうえでポイントとなるのが、高齢者・子ども・障がい者など、身体能力やニーズが大きく異なる人々へ対応する視点です。一つひとつの事例を具体的に挙げながら、どのような設計が求められるかを見ていきましょう。
高齢者
•歩行や視力などに不安がある人でも安全に移動・生活できる仕組み
階段や廊下に手すりを設置する、段差をなくす、床材を滑りにくい材質にするなどが基本的な対策です。照明計画も重要で、足元を明るく照らすLED照明や人感センサーライトを導入することで、転倒リスクを減らせます。
•ヒートショック対策
冬場に起こりがちな急激な温度変化を防ぐため、浴室や脱衣所の断熱性能を高める、暖房設備を導入するといった配慮も欠かせません。
子ども
•転落や指挟みなど事故を防ぐ工夫、遊びやすく安全な空間
子どもは活発に動き回るため、階段や吹き抜け部分の落下防止柵や、扉の指挟み防止パーツなどを設置すると安心です。キッチンにチャイルドロックを付ける、コンセントを高めの位置にするなど、子どもの安全を確保するアイデアを盛り込むことが多いでしょう。
•視線の確保
親が料理や家事をしながらでも、子どもの様子を確認しやすいよう、LDKをオープンにつなげる間取りや対面キッチンを選ぶケースが増えています。
障がい者
•車いすや視覚障がいなど多様なケースを想定
車いす利用が想定される場合は、廊下や開口部の幅を広く取り、スロープや手すり、片開きの自動ドアなども検討対象となります。視覚障がいがある場合には、床の色やテクスチャの違いを利用してゾーニングする、点字ブロックを活用するなどの工夫が考えられます。
•ユニバーサルデザイン規格
ドアノブやスイッチなどは、片手で容易に操作できる形状や位置が重要であり、JISやISOなどの規格で標準化が進んでいます。
パナソニックホームズ(パナホーム)の手すり配置例
実際にユニバーサルデザインを積極的に取り入れている住宅メーカーの一つが、パナソニックホームズ(旧パナホーム)です。同社では、手すりの配置や高さを施主家族のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズする取り組みが行われています。
•手すりの段差や高さ
階段だけでなく、廊下やトイレ、浴室など、立ち座りや移動の多い場所に手すりを配置。子どもや高齢者がよく使う場所には、二段手すりを設ける場合もあります。たとえば、上段の手すりは大人用、下段の手すりは子どもの身長に合わせるといった工夫が可能です。
| 会社名 | 株式会社松栄パナホーム熊本 |
| 所在地 | 熊本県熊本市南区田迎1丁目7-14 |
| 電話番号 | 096-379-4020 |
| 設立 | 1995年 |
| 対応可能エリア | 熊本県下一円 |
| 公式サイトURL | https://www.kumamoto-panahome.co.jp/ |
| レビュー |
◯あわせて読みたい記事
安い注文住宅とは?ローコストにできる理由と選ぶときのポイント
将来を見据えた間取りと設備
人生100年時代とも言われる現代では、住宅設計においても「現在の暮らし」だけでなく「将来の家族構成や介護、ライフスタイルの変化」を視野に入れることが極めて大切です。若い頃は段差があっても気にならなかったり、狭い廊下や出入口でも不便を感じなかったりするかもしれません。
しかし、長い年月のなかで年齢を重ねたり、家族の事情が変化したりすると、急に暮らしづらくなるケースが少なくありません。ここでは、高齢になっても快適に生活できるユニバーサルデザイン住宅の視点から、フラットフロアや広い廊下などの間取りに注目し、さらに具体的なプラン事例について解説します。
人生100年時代に対応する住宅設計
近年は平均寿命が伸びており、ライフステージの変化がこれまで以上に多岐にわたることが想定されます。たとえば、子育てが一段落したと思ったら、次は親の介護が始まったり、あるいは二世帯同居で新たな家族構成となる場合もあるでしょう。こうした状況に柔軟に対応するためには、「あらゆる年齢や身体能力を持つ人が快適に暮らせる設計」を、あらかじめ考慮しておくことが重要です。
•二世帯同居や介護など、ライフステージの変化を想定
将来、親を迎え入れて同居する可能性があるなら、寝室やバスルームを1階に配置する、必要に応じて車いすや歩行器でも動きやすいよう通路幅やドア幅を十分に確保しておくなどの工夫が考えられます。小さい子どもがいる家庭でも、階段や水回りを安全に利用できるよう段差や滑りやすい床材を見直しておくと、年齢やシチュエーションを問わず住みやすい家につながるでしょう。
•ユニバーサルデザインを取り入れた“将来予防”
特に介護が必要になってからバリアフリー改修を行うと、大幅なリフォーム費用がかかるケースがあります。それよりも、初めからユニバーサルデザインを取り入れておくことで、将来的な工事費用を抑えられる可能性が高まります。手すりを設置しやすい壁の下地を準備しておく、出入口を引き戸や折戸にしておくなど、わずかな工夫が将来の暮らしを大きく変えるのです。
フラットフロア・広い廊下
段差を極力なくす
ユニバーサルデザイン住宅を考慮する際の大きなテーマが、屋内外の段差をできる限り減らすことです。段差があると、つまずいて転倒するリスクが高くなるだけでなく、車いすやベビーカーの移動が難しくなります。特に玄関とリビング、廊下と居室の境目など、日常的な移動が集中する場所に小さな段差があるだけで、暮らしに大きなストレスが生じることも。そこで、設計段階から「床の高さを揃える」「スロープでカバーする」「ドアの下枠をなくす」など、段差を解消するプランを盛り込むのがおすすめです。
•玄関アプローチ
玄関先にスロープや屋根を設けることで、雨の日でも車いすやベビーカーが安全に出入りできます。また、段差の解消だけでなく、すべりにくいタイルや手すりを設置しておくと、高齢者の転倒予防にも役立つでしょう。
•浴室や脱衣所
段差の多い場所の代表格が浴室ですが、脱衣所との間に段差があると足元が不安定になります。フルフラットにする、滑りにくい床材を選ぶ、シャワーチェアなどを使えるスペースを確保するなど、転倒リスクを最小限に抑える設計が大切です。
廊下や出入口の幅を確保
もう一つのポイントとして、廊下や出入口の幅を広めに設計しておくことが挙げられます。通常の住宅であれば、廊下幅は約75~80cm程度が一般的ですが、車いすやベビーカーの利用を想定するなら、90cm以上、できれば100cm程度を確保すると余裕をもって通行しやすいでしょう。
出入口の幅に関しても、60~70cmが当たり前だった従来の規格から、80cm以上の開口がある引き戸や折戸にすることで、移動の快適性が大幅に向上します。
•ベビーカーや車いすの通行をスムーズに
子育て中はベビーカーが活躍し、高齢になると車いすや歩行器を使う可能性が高まるため、どの段階でも楽に移動できる幅を想定するのが理想です。狭い廊下や狭いドアでは、一人が利用しているだけでも家族とのすれ違いにストレスを感じることがあるため、数十センチの余裕が将来的には大きな意味を持ちます。
•収納の出し入れや家具配置も快適に
廊下の幅が広いと、引っ越しや家具の入れ替えなどの際にも移動がしやすく、生活全体の利便性が高まる点も見逃せません。
シアーズホームの柔軟なプラン
引用元:シアーズホームHP
熊本エリアで注目を集めるシアーズホームでは、将来を見据えたユニバーサルデザインへの取り組みを行っており、施主のライフステージに合わせて柔軟な間取り変更ができる構造を提案しています。以下では、同社のプラン事例や実際の施主の声を紹介します。
将来のリフォームを想定
シアーズホームでは、家づくりの段階から壁や柱の配置を工夫し、子どもが独立した後や親との同居が始まった際に、間仕切りを変更して部屋数を調整できるように設計する例が多いそうです。
また、電気配線や給排水のルートを余裕を持って設計しておくことで、キッチンや洗面台などの移設・増設を行いやすくする狙いもあります。こうした“将来予防”ともいえる配慮により、大掛かりなリフォーム工事を避けながら、ライフステージの変化に対応することが可能です。
| 会社名 | 株式会社シアーズホーム |
| 所在地 | 熊本県熊本市南区馬渡2-12-35 |
| 電話番号 | 096-370-0007 |
| 設立 | 平成元年1月17日 |
| 対応可能エリア | 熊本県、福岡県、佐賀県 |
| 公式サイトURL | https://searshome.co.jp/ |
| Googleレビュー | レビューなし |
ユニバーサルデザイン住宅では、高齢者や子ども、障がい者などを想定するだけでなく、「自分自身が将来どのような身体状況や家族構成になるか」を見越しておく視点が求められます。人生100年時代において、数十年先まで家族が安全に暮らせる空間づくりを考えれば、フラットフロアや広い廊下はもちろん、リフォーム前提の壁配置や設備設計も有効な選択肢となるでしょう。
次セクションでは、さらにスイッチやドア位置など、より細かな工夫について解説し、ユニバーサルデザインを住宅の隅々にまで行き渡らせる具体的アイデアを紹介します。
◯あわせて読みたい記事
シアーズホームの断熱最高等級7に対応した高性能住宅な家づくり
スイッチ・ドア位置の工夫
引用元:すむたまHP
家づくりにおいて意外と見落とされがちなのが、スイッチやドアの配置や高さです。多くの方は自分たちの身長や使い勝手に合わせて「これくらいで大丈夫だろう」と感覚的に決めてしまいがちですが、将来的に身体能力が低下することや、子どもや車いす利用者が暮らす状況を考慮すると、少しの違いが大きな利便性の差につながります。
たとえば、車いすに乗ったままでも容易に手が届く高さにスイッチを設置しておけば、高齢になって歩行が困難になった後も、わざわざ体を伸ばして操作する負担がなくなるでしょう。ここでは、ユニバーサルデザインの視点から、使う人の身体能力や生活スタイルを踏まえたスイッチ・ドア位置の決め方を解説します。
使う人の高さや身体能力に合わせる
子ども、高齢者、車いす利用者などが無理なく操作できる位置
ユニバーサルデザイン住宅では、「誰が使うか」を考慮しながら、スイッチやドアノブの取り付け高さ、形状、配置などを検討するのが基本です。子どもがいる家庭であれば、子どもの目線や手の届く範囲を意識してスイッチの高さを決めると、成長してからも使いやすく感じることが多いでしょう。高齢者の場合は、しゃがんだり腕を大きく伸ばしたりする動作が負担にならないよう、ほどほどの高さに統一しておくと、立ち座り時の身体の負担が減らせます。
•車いす利用者向けの配慮
車いすのシート高は40~50cm程度が一般的と言われます。手を伸ばしやすい範囲を想定すると、スイッチは80~100cm前後が操作しやすい高さの目安です。さらに、奥まった位置に設置すると車いすのままでは届きにくいことがあるため、廊下の端やドアの近くに設置しないよう気を付けるのも重要。
•家族全員の目線調整
スイッチの場所は家族で身長差がある場合、二段設置を検討するケースもあるでしょう。1つは大人用、もう1つは子どもや車いす利用者が操作しやすい高さにするといった工夫で、年齢や身体状況が違う家族がともに快適に暮らせる可能性が高まります。
ユニバーサルデザイン規格準拠
ユニバーサルデザインを住宅に取り入れる際には、JIS規格や国際標準などで提唱されているUD規格に準拠する形で設計すると、より具体的な数値基準を参照できるメリットがあります。ここでは、UD規格の概要と、スイッチ・ドアノブなどの住宅パーツに関してどのように標準化が進んでいるのかを見ていきましょう。
UD規格の概要
ユニバーサルデザインに関する基準やガイドラインは、国内外で徐々に整備されてきました。日本では、JIS(日本産業規格)において、人体寸法や機能特性を考慮した設計の指針が示されています。たとえば、身長別の「使いやすい高さ」や「操作しやすい力の範囲」などが具体的な数値で示されており、こうしたデータを参考に設計・施工を行うと、より多くの人が不便を感じにくい住宅に近づけることができます。
•JIS規格で示される人体寸法や機能特性
人体寸法の実測データをもとに、座位や立位での操作範囲、腕のリーチ、脚の可動域などがまとめられています。高齢者や障がい者だけでなく、子どもや女性なども含めた幅広い実測データがあるため、汎用性の高い設計が可能です。
•スイッチやレバーハンドルの標準化
ドアノブやスイッチは、片手で操作できる、力が入りにくくても開閉しやすいなどの要件がUD規格で推奨されることが多いです。具体的には、球形ノブではなくレバーハンドルを採用すると、腕に力が入りにくい高齢者や、指先の力が弱い子どもでもドアを開閉しやすくなります。スイッチ類は大きなパネル型にするとか、手が触れやすい位置に配置するといった形で、操作性を向上させる工夫が見られます。
地域密着工務店の細かな対応
ユニバーサルデザイン住宅の実現には、規格やガイドラインの知識だけでなく、施主のライフスタイルや地域の特性をきめ細かく反映させることが欠かせません。ここでは、地域に根ざした工務店がどのようにUD設計をサポートしているのか、熊本の例を取り上げて紹介します。
地元特有の気候・生活様式への対応
熊本のように高温多湿な気候で、さらに台風や豪雨といった自然災害が多い地域では、通常のユニバーサルデザインに加え、湿気対策や防水・排水計画、耐風設計なども同時に考慮する必要があります。
たとえば、玄関付近にスロープを設けても、台風の時期に強い雨風が吹き込む恐れがあるなら、屋根の深さや庇(ひさし)の形状を工夫しなければなりません。また、屋内外の段差をなくすと床下へ雨水が侵入しやすくなるケースもあるため、排水勾配や防水シールなどを厳密にチェックする必要があります。
施主の相談に応じたカスタマイズ
地域密着の工務店は、施主のライフスタイルや身体状況を直接ヒアリングしながらプランを調整できるメリットがあります。たとえば、車いす利用者が家族にいる場合は、廊下やドア幅、スイッチの高さだけでなく、トイレや洗面台の形状・高さなどにもきめ細かく対応。あるいは、子育て中の家庭であれば、子どもの成長に合わせてロフトや収納を柔軟に増設できるような下地工事を行うなど、自由度の高いプラン提案が可能です。
•施主の身体状況や家族構成に合わせ、自由度の高いプラン提案
「玄関は車いすでも通りやすい引き戸にしたい」「洗面化粧台の下をオープンスペースにして脚が入るようにしたい」など、施主の要望に合わせて細かいカスタマイズができる点が、地域工務店の強みと言えます。加えて、万一住んでから「やっぱりもう少しスイッチを高く/低くしたい」というニーズがあれば、近場にある工務店が迅速にリフォーム対応できる安心感も大きなメリットでしょう。
スイッチやドア位置などの細かな部分は、普段あまり意識しないかもしれません。しかし、ユニバーサルデザイン住宅を成功させるには、こうしたディテールの配慮こそが大きな差となります。使う人の身長や身体能力、将来の変化を見据えて適切な高さや配置を検討することで、日常生活が格段に快適になり、転倒や事故のリスクも減らせます。また、地域密着の工務店を選べば、地元の気候風土や家族の具体的な事情を踏まえたカスタマイズが可能です。
次のセクションでは、これまで解説してきた「ユニバーサルデザイン住宅」の考え方や具体策を振り返りつつ、読者が実際に家づくりを進める際のアクションプランについて提案します。誰もが暮らしやすい住まいを実現するためには、段差解消やスイッチ位置だけでなく、ライフサイクルや地域特有の課題なども総合的に視野に入れることが鍵となるのです。
◯あわせて読みたい記事
地域密着型の家づくりとは?工務店とハウスメーカーの違いと選び方のポイント
まとめ
ユニバーサルデザイン住宅は、バリアフリーを含む包括的な設計思想であり、家の中の段差解消や手すり設置だけでなく、スイッチ位置やドア幅など、あらゆる面で誰もが快適・安全に暮らせる住まいづくりを目指します。こうした取り組みは高齢者や障がい者だけでなく、子どもや一般成人にとっても利便性を高める結果となり、家族全員が長く快適に過ごせる家になるでしょう。
これから家づくりを検討する方は、ぜひ資料請求やモデルハウス見学を通じて実際の手すり設置や段差解消、スイッチ位置などのUD事例を確認してみてください。耐震・断熱などの要素も含めて、将来を見据えた間取りや設備の柔軟性を考慮することが大切です。地域密着の工務店や大手ハウスメーカーに相談し、家族構成や将来のライフイベントに合わせた最適なアプローチを見つけましょう。
◯あわせて読みたい記事
地域の木材で作る新産住拓~家族の絆を深める住まいとは?